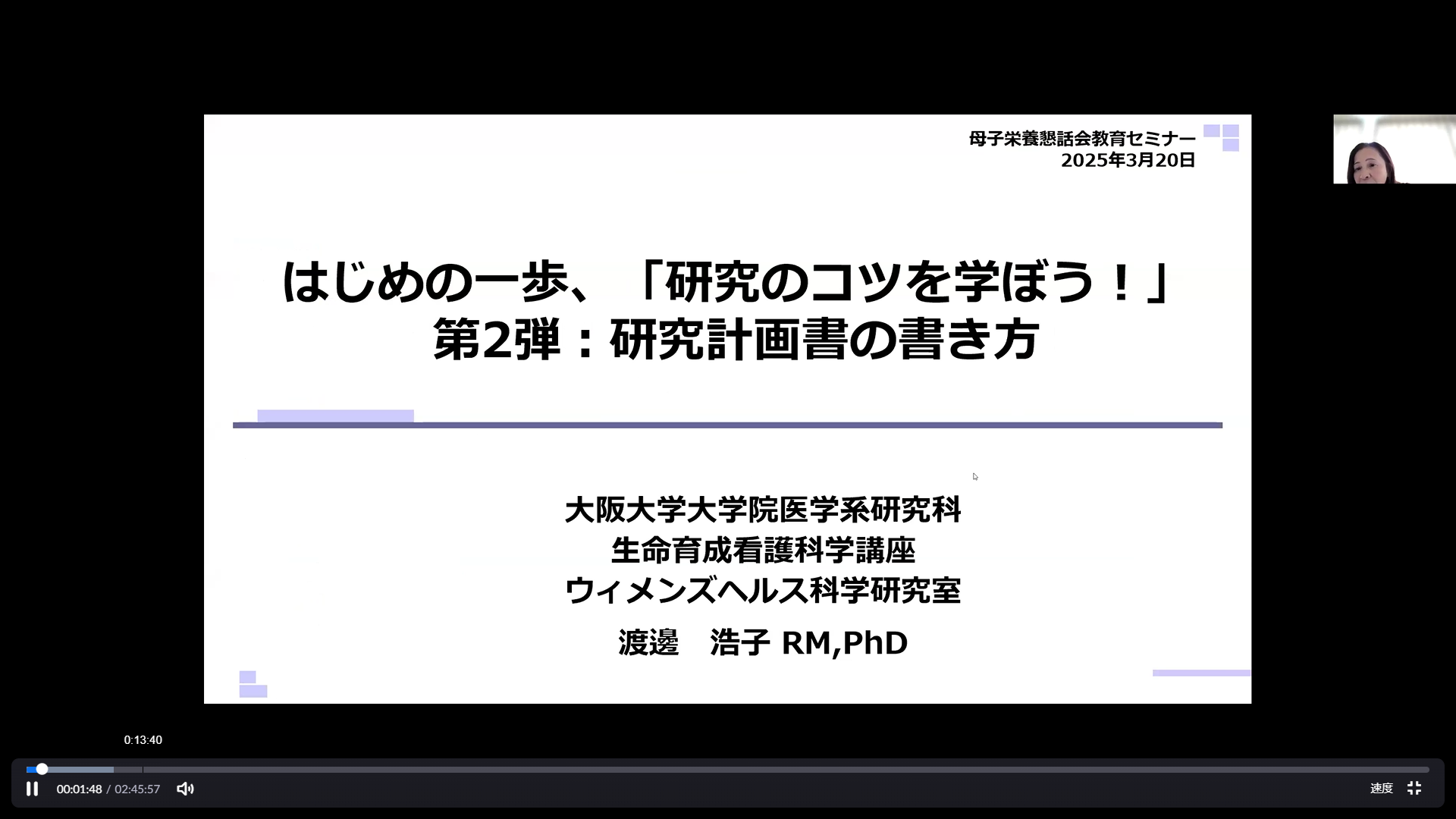栄養科ブログ
栄養にまつわるさまざまなこと、お料理や食事について、私たち管理栄養士や調理師にお気軽におたずねください。
私たちは「食」を通じて、当院を訪れる皆さまの健康や幸せ作りのお手伝いができればと思っております。
栄養士の仕事の‘‘ウラガワ‘‘ 研究を学ぶ講座2回目参加レポート⑴
♡今回のブログは前回に引き続き、研究に興味がある方向けです♡
https://www.nagai-cl.com/nutrition-blog.php?y=2025&m=3&d=7
祝日の木曜日、母子栄養懇話会が開催する講座に朝から約3時間、学んで来ました。
テーマは‘‘医療者がカジュアルに院内発表までの方法を学ぶ‘‘ はじめの一歩、皆でやってみて 「研究のコツを学ぼう!」
私達の身の回りにある薬や政府の政策などは、『研究』を通して根拠を持って世の中に発信されることが多いです。テレビやネットで見かける食べ物に関しての情報、すぐに信じていませんか?それって本当に正しい情報ですか?
今回は、臨床の現場で見つけたテーマを大阪大学大学院の渡邊浩子先生のご指導の基、研究デザインを設定しました。
-----『研究』までのプロセスとは?
➀ 臨床的な疑問(CQ:クリニカルクエスチョン)
↓
② 研究形式に変換(RQリサーチクエスチョン)
↓
③ RQのブラッシュアップ
↓
④ 研究のデザインを決定(介入研究か?観察研究か?)
↓
⑤ 倫理的配慮(対象者のプライバシーを侵害していないか?自分の欲だけを満たす研究ではなく、社会のニーズに答えているか?)
↓
⑥ 研究計画書(プロトコル)の作成
↓
⑦ 研究チーム編成
↓
⑥ 倫理委員会の承認(第三者委員会からの承認が必要)
↓↓
おめでとう、やっと研究スタート!(ここまで約3か月かかると言われている。)ひゃー!
どうしてここまで大変な過程を介さないといけないのか?
次回、理由と具体例を挙げて紹介~To be continued~
HARUYAMA